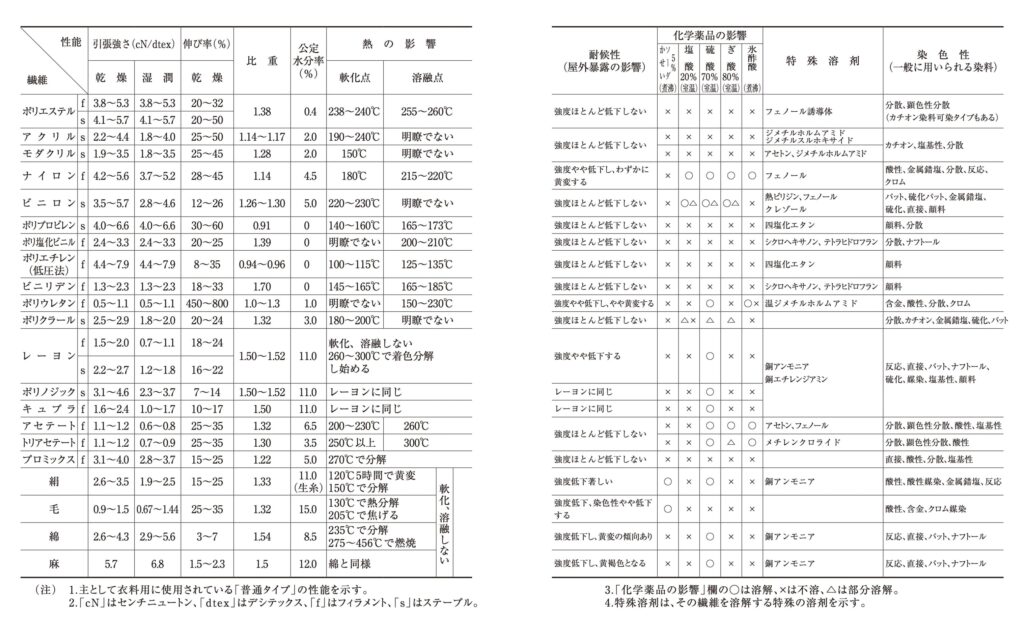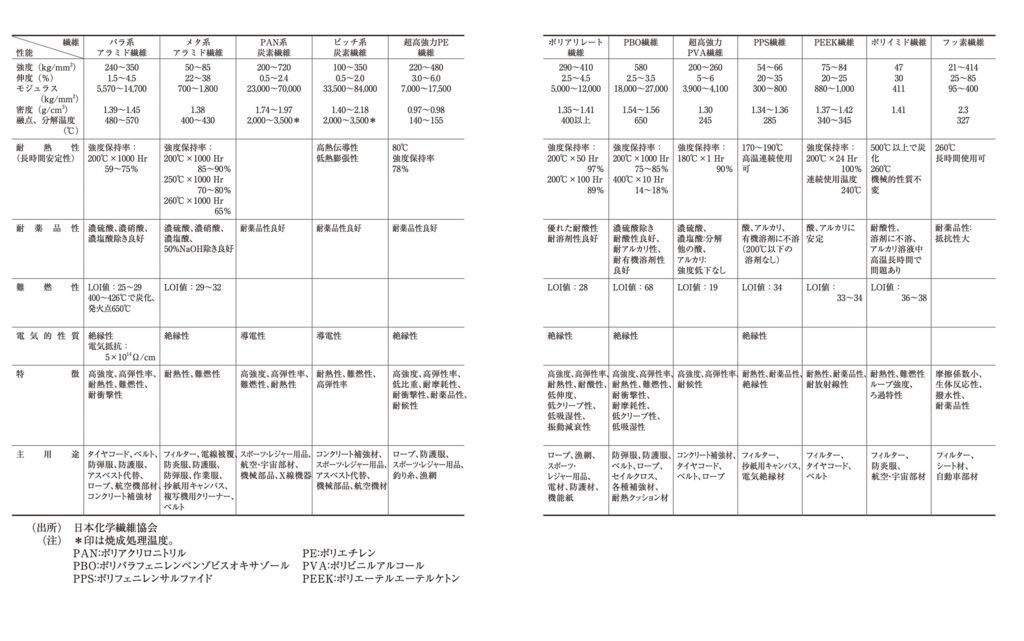化学繊維は、天然の木材などから精製されたセルロースを原料とする再生繊維、セルロースやタンパク質などの天然高分子を化学的に処理して原料とする半合成繊維、石油などから合成した高分子材料を原料とする合成繊維、無機物を原料とする無機繊維の4種類に分類されます。
①ポリエステル
ポリエステル繊維にはPET(ポリエチレンテレフタレート)、PTT(ポリトリメチレンテレフタレート)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)などがあります。最も生産量が多いのはPETで、一般的にポリエステルといえばPETを指します。PETはテレフタル酸とエチレングリコールが縮合重合してエステル結合で結ばれたポリマー(重合体)です。ペットボトルの原料もこのPET樹脂です。このPET樹脂を高温で加熱溶融し、小さな孔がたくさん開いた口金から押し出して空気中で冷却し、繊維化したものがポリエステル繊維です。この紡糸方式を溶融紡糸といいます。ポリエステルには絹のように連続した長繊維(フィラメント)と木綿や羊毛のようなわた状の短繊維(ステープル)があります。フィラメントはそのまま使うか、またはほかの繊維と合撚したり、嵩高加工を施すなどして、編物や織物になります。ステープルは木綿、羊毛などの天然繊維やほかの化学繊維と混紡して、各々の長所を生かした製品が作られています。ポリエステル、ナイロン、アクリルは三大合繊と呼ばれており、その中でもポリエステルは、比較的容易に製造できることや繊維性能のバランスが優れていることから様々な用途で使われており、世界で最も多く生産されている化学繊維です。
②ナイロン
ナイロンは化学繊維の中でも長い歴史を持つ合成繊維の一つです。1935年、米国デュポン社のカロザースが合成に成功しました。当時、主に絹で作られていた薄手のストッキングに着目し、1939年ナイロンストッキングを発売しますが、当時のキャッチフレーズは「石炭と水と空気から作られ、鋼鉄よりも強く、クモの糸より細い」というものでした。ナイロンは本来、登録商標名でしたが、現在ではポリアミド系繊維(縮合重合してアミド結合(-CO-NH-)で結ばれた重合体)の総称として定着しています。主なナイロンとしては、ナイロン6、ナイロン6,6などがありますが、これらの数字は、原料の炭素原子の数に由来しています。カロザースが合成したのはナイロン6,6です。一方、ナイロン6は1941年に日本で開発されました。衣料用で多く使われ、生産量の多くは長繊維ですが、羊毛や綿などとの混紡用として短繊維も生産されています。一方、ナイロン6,6は耐熱性や強度が優れているため、タイヤコード、漁網、シート、ロープなどに使われています。
③アクリル
アクリル繊維は、アクリロニトリルを主成分とする合成繊維です。アクリロニトリル100%の繊維は紡績と染色が難しいため第二成分を共重合して改質しています。このアクリロニトリルの含有量でアクリル繊維とモダクリル繊維とに分類されます。JIS規格では、質量比でアクリロニトリル85%以上をアクリル繊維、35%以上、85%未満をモダクリル繊維と定義しています。アクリロニトリル重合体は高温で加熱しても溶融せずに炭化するため、溶剤に溶かして、口金の孔から押し出して繊維化します。繊維化する方式は、口金の孔から溶剤と水との混合液中に押し出して溶剤を抜く湿式紡糸法と、口金の孔から熱風中に押し出して溶剤を蒸発させる乾式紡糸法とがあります。湿式紡糸は有機溶剤あるいは無機溶剤が使われ、乾式紡糸は有機溶剤が使われます。製造方法の違いによって、繊維断面、光沢、手触り(風合い)などが異なります。アクリル繊維は他の合成繊維と比べると、最も羊毛に似ており、発色性、嵩高性、耐候性に優れています。短繊維は、綿や羊毛など他の繊維と混ぜて各々の長所を生かした紡績糸が作られ、衣料やインテリア・寝具用で使われています。モダクリル繊維は第二成分に塩化ビニルや塩化ビニリデンが使われており、難燃性に優れるため、難燃カーテンや難燃毛布などに使われています。人工毛髪やエコファーにもモダクリル繊維が使われています。
④ビニロン
日本で発明され、工業化に成功した国産初の合成繊維です。合成繊維の中では最も吸湿性があり、綿に似た合成繊維といわれています。軽くて、耐久性と耐候性に優れることから、工業用、農業用、漁業用をはじめとして産業用途で広く使われています。アルカリに強く、セメントとの親和性が良いため、現在は使用が禁止されているアスベストに代わるセメント補強材として使われています。短繊維が中心ですが、長繊維もあります。長繊維は絹に似た風合いを持ちます。
⑤ポリプロピレン
石油精製品の一つであるプロピレンを重合して製造したものです。合成繊維の中で最も軽く、水に浮きます。耐久性、耐薬品性、防汚性などの特長を生かして、インテリア、ロープなどの産業資材を中心に使用されています。吸湿・吸水性がないため速乾性に優れます。熱伝導率が低いため、保温性に優れた温感素材として注目されています。融点が低いことが欠点である一方、この特徴を生かし、熱で溶けて自己接着させた不織布が衛生材料などで使われています。
⑥ポリ塩化ビニル
世界で最も早く発明された合成繊維で、1931年にドイツで発明されました。石油由来のエチレンと食塩水を電気分解して得られる塩素とを反応させて得られる塩化ビニルを重合したポリ塩化ビニルを溶融紡糸して繊維化したものです。難燃性、耐薬品性、耐久性、耐候性に優れ、保温性にも富んでいます。ほかの繊維と摩擦するとマイナスの静電気に帯電するため、健康肌着などで使われてきました。耐熱性に劣るため、アイロンがけを必要とする衣服には使えません。
⑦ポリエーテルエステルエラストマー
プラスチックとゴムの中間の性質を持つ素材です。プラスチック構造としてポリエステル(主にPBT)構造を、ゴム構造としてポリエーテル (主にポリテトラメチレンエーテルグリコール)構造を用いたブロック共重合体です。これらの構造の割合によって様々な特徴を持つポリマーが合成可能となります。このポリマーを特殊な紡糸方法でループを描きながら三次元方向につながった三次元網状繊維構造体に成型したものは通気性・耐久性に優れたクッション材として使われています。
⑧ポリエチレン
エチレンを重合したポリエチレンを繊維化したものです。非常に軽くて強い繊維ですが耐熱性はあまりよくありません。用途は紐やロープ類、畳糸、ろ過布、釣り糸、防虫網などの産業資材が中心です。一方で熱伝導率が高いため、接触冷感素材として夏用の敷きパッドや枕カバーなどの寝装用途を中心にハンカチやネッククーラーなどにも使われています。超高分子量ポリエチレン繊維については別項で説明します。
⑨ビニリデン
塩化ビニルと塩化ビニリデンを共重合し、繊維化したもので高い難燃性があります。耐薬品性に優れるため、薬品を塗布して使う防虫網や化学薬品の液体ろ過にも使用されています。摩擦に強く、比重が1.7と大きいため、沈降ロープや漁網など、水中に沈める用途で重宝されています。他の合成繊維に比べて柔らかく感じられ、滑らかな風合いになることから、人形の髪の毛にも使用されています。また、他素材に比べて擦過を起こしにくいことから人工芝でも使われています。
⑩ポリウレタン(スパンデックス)
ポリウレタンはゴムのように伸び縮みする繊維です。グリコールとジイソシアネートとの重付加反応で得られる重合体を溶剤に溶かし、乾式紡糸または湿式紡糸で繊維化します。100%使いの製品はなく、他の繊維と混ぜて利用されています。ポリエステルなどと一緒にポリウレタンを編み込んだ2ウェイ(縦横2方向に伸縮可能)トリコットは水着、スポーツウェアなどに使われます。ポリウレタンを芯にナイロンなどで巻きつけた糸はカバード糸と呼ばれストッキングやボディファンデーションに使われます。紡績工程でポリウレタンを芯に挿入したコアスパン糸や他の繊維と合糸して撚糸したプライ糸は婦人服やジーンズなどに使用されています。快適な着心地が好評で、展開アイテムも増えています。
⑪エチレンビニルアルコール
エチレンとビニルアルコールの共重合体を鞘にポリエステルを芯にした複合構造の繊維です。合成繊維でありながら、綿や麻のように水との親和性が高い親水基(OH基)を持ち、吸湿・吸水、水分の拡散性に優れています。天然繊維よりも優れている点が速乾性です。水分を素早く吸収し、拡散して乾燥させることができるからです。冷感、速乾、光沢などの特長を持ち、冷感素材としてシャツや寝装用途に使われています。また、汚れが落ちやすいことから靴下用としても使われています。
⑫ポリ乳酸
ポリ乳酸はポリエステルの一種で、その名称の通り、乳酸が連なってできています。製造過程で、トウモロコシなどの植物からデンプンを抽出し、酵素で加水分解してグルコース(ブドウ糖)を生成します。このブドウ糖を乳酸菌による発酵でL-乳酸を得ます。この乳酸を縮合重合してできたポリ乳酸を溶融紡糸して繊維化します。生分解性があり、土中に埋めると微生物によって水と炭酸ガスに分解されるため、自然循環型の繊維として注目されています。生活雑貨や衣料用でも使われており、圧電性(伸び縮みすると、電圧が発生する性質)を利用した、抗菌素材やスマートテキスタイルにも応用されています。
⑬ポリイミド
ポリイミドの誕生は、60年前にさかのぼります。米ソ宇宙開発競争が盛んであった1960年代に軍事的要求から生まれました。1970年代には耐熱性を生かした樹脂の展開が始まりましたが、繊維への展開は困難を極めました。しかし1985年、オーストリアのレンチング社が試作に成功し、その後、ポリイミド繊維の本格生産が始まりました。ポリイミドは大別すると縮合反応型と付加反応型がありますが、繊維化に成功したのは縮合型の芳香族イミドのポリマーです。ポリイミド繊維は乾式紡糸法により、繊維1本1本が不均一な異形断面を持つため優れた集塵性能を発揮します。また耐熱性にも優れるため、工場などの排ガス処理用の耐熱フィルターに適しています。
⑭アクリレート
アクリル繊維の改質により超親水化した繊維です。アクリル繊維のニトリル基をアルカリで反応させて親水基(カルボキシル基、金属塩基等)に変換します。そのままでは水に溶解してしまうため架橋剤で高分子間を架橋します。親水基が天然繊維よりも多いため非常に高い吸湿性能を有しています。吸放湿は可逆的で乾燥状態では、一度吸った水分を放出します。また湿気を吸うと吸着熱により発熱するため暖かくなります。冬季に適した素材で、衣服や寝装品などの着用時に体表面の温湿度を調整して、快適性を保ちます。
⑮ポリフェニレンサルファイド(PPS)
ポリフェニレンサルファイドの頭文字をとってPPSと呼称しています。耐熱性に優れた熱可塑性エンジニアリングプラスチックで、これを溶融紡糸して作る高性能繊維です。融点は285℃で、酸・アルカリ・有機溶剤への高い耐性、難燃性に加え、他の高性能繊維にはない優れた耐加水分解性も持ち合わせています。このような性能を利用して、焼却炉やボイラーなどの高温排ガスから微粒子などを取り除く耐熱フィルター(バグフィルター)や抄紙用資材(フェルトやドライヤーカンバス)などで使われています。
⑯炭素繊維
炭素繊維は大きく分けて、原料の異なる2種類に分類されます。アクリロニトリル純度の高い特殊なアクリル繊維を高温焼成して炭化するPAN(ポリアクリロニトリル)系炭素繊維と、ピッチ(石炭や石油・コールタールの副生成物)を紡糸し、不融化後、高温で炭化するピッチ系炭素繊維があります。市場に流通している炭素繊維の大半はPAN系炭素繊維です。炭素繊維単体では形状が保持できず、一般的には炭素繊維を引き揃えたもの、織物や編地にしたものをエポキシ樹脂などのプラスチックで固めた炭素繊維強化プラスチック(CFRP)として使用します。PAN系、ピッチ系共に弾性率が高く、特にPAN系は「軽量・高強度」が特長で、航空宇宙や産業分野の構造材料向け、自動車、スポーツ・レジャー分野など広範囲な用途で使われています。一方、ピッチ系は「軽量・高剛性」が特長で、加えて熱伝導が高く、熱膨張が極めて小さいことから産業用ロボットアーム、人工衛星、宇宙望遠鏡などで使用されています。
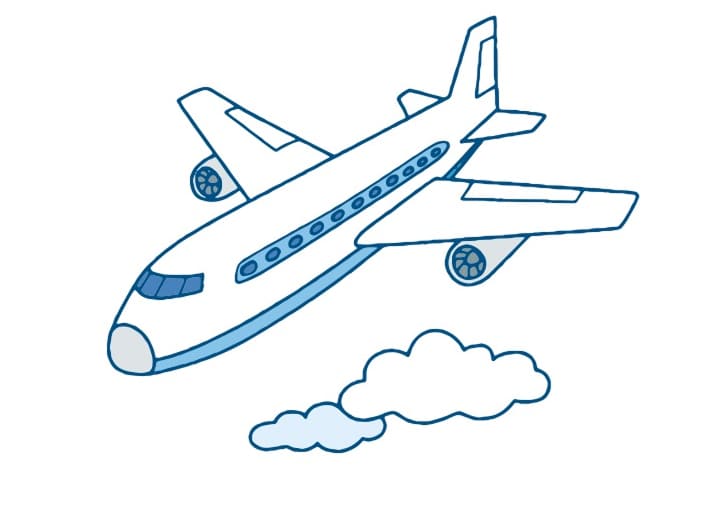
⑰アラミド
アラミドはナイロンと同様にアミド結合によってできたポリアミドで、ナイロン(脂肪族ポリアミド)とは異なり、ベンゼン環を含む芳香族ポリアミドです。その構造によりパラ系とメタ系があります。パラ系アラミドの特長は高強度、高弾性率です。鋼材と比較して引張り強力が約7倍、重量が約5分の1と高強度かつ軽量です。また耐久性が高く、耐薬品性や耐熱性にも優れた繊維です。このような特長から、様々な分野での補強材、防弾チョッキ・消防服・防護(防刃)手袋などの防護衣料、さらには耐熱フェルト、ブレーキパッドのような摩擦材など産業資材用途で幅広く使われています。メタ系アラミドは耐熱性、難燃性に優れており、消防服、レーサー服、高温作業服などで使用されています。
⑱超高分子量ポリエチレン
通常のポリエチレンの分子量は数万から20万程度ですが、超高分子量ポリエチレンは100万以上にもなります。この超高分子量ポリエチレンをゲル紡糸法と呼ばれる特殊な紡糸方法で、ゼリー状に固まったゲル状物質を高倍率に延伸すると、高分子鎖が一方向に引き揃えられて、高強度な繊維となります。この超高分子量ポリエチレン繊維の強度は鉄鋼を素材とするピアノ線の8倍にもなります。高強力・高弾性率に加えて、耐摩耗性、耐疲労性、衝撃吸収性や耐侯性、耐薬品性などにも優れ、水に浮くほどの軽量性もあります。船舶用係留ロープや釣り糸、防護(防刃)手袋、ヘルメットなどの安全用具で使用されています。そのほか、土木・建築資材の補強材や高熱伝導性を生かした接触冷感寝装用途での利用も拡大しています。
⑲高強力ポリアリレート
高強力ポリアリレートは、全芳香族ポリエステル(ベンゼン環で構成され、その結合部分がエステル結合からなる高分子)を溶融紡糸法によって繊維化したものです。原料の高分子は結晶と液体の中間的な状態にある液晶高分子で、一般的には成形用樹脂として扱われています。繊維化する場合は繊維状にしてさらに熱処理を施して強度を向上させます。この繊維は強度が通常のポリエステルの約4倍あります。ほかにも高弾性率、低吸湿性、耐摩耗性、寸法安定性に優れ、切断しにくいなどの特長から、漁網、ネット、ロープなどで使われています。衝撃吸収性に優れるためNASAの火星探査機着陸用エアバッグにも採用されました。
⑳PBO
PBOとは、ポリパラフェニレンベンゾビスオキサゾールの頭文字をとった略称で、1998年に商品化された高性能繊維です。この繊維の特徴は、ベンゼン環にヘテロ環を組み込んだ剛直な構造の高分子を液晶紡糸して高い分子配向を実現していることにあります。合成繊維の中で最も高い強度・弾性率・耐熱性を有し、引張り強度・弾性率は同じベンゼン環を持つパラ系アラミド繊維の約2 倍です。高強度・高弾性率を生かした用途としては伝動ベルト、自転車のチューブレスタイヤやスポーク、ヨットロープ、テニスラケット、卓球ラケット、スノーボードなどスポーツ用途があります。主力用途は優れた耐熱性や難燃性を生かした消防服や耐熱フェルトで、その他、レーサー服、耐熱防護服などにも使われています。
㉑フッ素繊維
「こびり付かないフライパン」のテフロン加工で知られるフッ素(PTFE)樹脂はフッ素原子(F)が炭素原子(C)を覆いつくす強固なCF結合を持つ樹脂です。この化学的に不活性で強固な樹脂をエマルジョン紡糸と呼ばれる特殊な紡糸方法で繊維化したものです。耐熱性、耐薬品性に優れ、かつ低摩擦性、低粘着性、撥水性、防汚性、電気絶縁性などにも優れています。 これらの特長を生かし、バグフィルター、電線被覆、食品工場や製薬工場などのコンベヤベルトなどを中心に幅広く産業分野を支えています。
㉒アセテート
アセテートフィラメントはレーヨンの主原料であるパルプに酢酸を反応させたアセチルセルロースを溶剤に溶かし、乾式紡糸で繊維化します。100%の植物由来原料ではなく100%の化学原料でもないので半合成繊維に分類されます。適度な吸湿性、放湿性、保温性があり、軽いのが特長です。付加するアセチル基の数で呼び名が異なり、アセチル基が2つ付いたものがジアセテート、3つ付いたものがトリアセテートです。トリアセテートは絹のような光沢と感触があり、ドレープ性に優れることから「美の繊維」と呼ばれ、婦人・紳士服、ユニフォーム、スポーツ衣料などに使われています。またジアセテートのトウ(連続した繊維束)はタバコのフィルターに使われています。
㉓プロテイン
プロテインというと、たんぱく質の補給を目的とした粉末を想像しますが、プロテイン(protein)とはたんぱく質のことです。たんぱく質でできた天然繊維といえば絹や羊毛ですが、今話題のプロテイン(構造たんぱく質)繊維は、植物由来の糖を主原料に微生物発酵して生産した人工たんぱく質を原料に使っており、これを紡糸して繊維化したものです。たんぱく質は20種類のアミノ酸の組み合わせでできており、用途に応じてその配列をデザインすることで、特性の違う様々な繊維を作ることが可能です。シルクのような光沢と繊細さを持つフィラメント糸、上質でなめらかな肌触りのカシミヤや嵩高性に優れたウールのような紡績糸に加工することもできます。
㉔レーヨン
レーヨンは日本で一番早く作られた化学繊維で、木材パルプのセルロース(繊維素)を取り出し、再生して繊維化するため、再生繊維に分類されます。吸湿・吸水性に優れ、深みのある美しい色に染まります。レーヨンの織物や編物は、ドレープ性に優れ美しいシルエットが表現できることから、ファッション衣料として使われてきました。レーヨンにはフィラメントとステープルがあり、服地、和装用品、裏地、下着、寝装具、カーペット、カーテン、使い捨てワイパーなどの様々な用途で使われています。
㉕ポリノジック
レーヨンが大量生産されるようになってからも、性能的にはまだ決して十分なものとは言えませんでした。綿に比べて強度が弱く、濡れるとさらに弱くなるため、同じ再生繊維でもそうした欠点のない新しい繊維はできないものかと、様々な研究と改良が進められ、誕生したのがポリノジックです。ポリノジックの原料はレーヨンと同じ木材パルプですが、製造方法が異なります。異なる点はセルロース高分子の重合度を高く保ったまま、結晶化度が高く、かつ断面が均一になるように繊維化することです。これにより、湿潤強度、弾力性を高め、寸法安定性が改良されました。
㉖キュプラ
キュプラは同じ再生繊維のレーヨンがパルプを原料としているのに対して、綿花の種子の周りにある短い繊維(コットン・リンター)を主原料にしています。原料を銅アンモニア溶液に溶かし、この溶液を湿式紡糸によって繊維化します。別名、銅アンモニア法レーヨンとも呼ばれます。キュプラは「銅(原子記号Cu)」を意味し、名前の由来は製造方法によるものです。キュプラは非常に細い糸ができ、絹に似た光沢があり、染色性に優れ、鮮やかに染めることができます。しなやかで肌触りがよいためボディファンデーションや裏地、薄地の生地などに使われています。
㉗リヨセル
リヨセルは、ユーカリの木材パルプを原料とし、NMMO(N-メチルモルフォリン-N-オキサイド)と呼ばれる溶剤を用いて紡糸した溶剤紡糸セルロース繊維です。従来のレーヨン系繊維の製造方法とは異なり、溶剤(NMMO)をほぼ完全に回収、再利用できることを特長とします。繊維断面は円形で、レーヨンと比較して強度が高く、湿潤時の収縮や強度低下が小さく、弾力性も備えます。ソフトな風合いで発色性や吸放湿性に優れることからファッション分野を中心に高い評価を受けています。
㉘モダール
レーヨンの一種ですが、ブナの木材パルプを原料にしています。レーヨンと比べて耐久性や柔軟性に優れており、肌触りの良さを特長とします。吸放湿性に優れ、水濡れに強く、縮み・型崩れ・毛羽立ち・色落ちがしにくい、シルクのような光沢と肌触りの良さを持つことから高級繊維として扱われています。発色性が良いため、単体でストールなどの衣料品にも使用されます。また、綿やリネンなどと混紡して、なめらかさやしなやかさをプラスすることができます。
㉙PHA
微生物の中には種々の脂肪族ポリエステルを生合成し、エネルギー貯蔵物質として体内に蓄積するものがあります。この微生物産生脂肪族ポリエステル(ポリヒドロキシアルカノエート)は、その頭文字をとってPHAと呼ばれます。PHAは糖や植物油を原料として微生物体内で生合成されるバイオマスプラスチックです。溶融紡糸や延伸条件などの技術も確立し、繊維製品として実用化が始まっています。PHAは自然界の海水や土壌に存在する微生物によって炭酸ガスと水に分解されることから炭素循環型の繊維として注目されています。
㉚その他(無機繊維)
無機繊維は、化学繊維の一種で、人工的な無機物の繊維で、ガラス繊維、炭素繊維、金属繊維、岩石繊維などがあります。無機繊維の特徴としては強度が高く、耐熱性、耐久性に優れていることから、産業資材分野で活用されています。ガラス繊維はグラスファイバーとも呼ばれ、熱や電気の絶縁性に優れた不燃材です。主に強化プラスチック用や断熱材として利用されています。炭素繊維はアクリル繊維などを焼成し、炭化させて作られます(「⑯炭素繊維」参照)。金属繊維は、複合材、ろ過材、除電材などで使われます。岩石繊維は、玄武岩繊維(バサルト繊維)とも呼ばれ、アスファルトやコンクリートの補強や耐熱性が要求される用途で使われています。